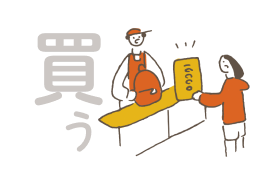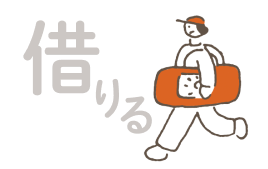ウッドストーブおすすめ18選!使い方や100均グッズでの自作方法も紹介
2023.09.25キャンプ用品
ウッドストーブとは、木の枝やまつぼっくりなどを燃やすことで出る自然のガスを利用する小型のストーブ。携行性や収納性が高く、調理もできるすぐれものです。この記事では、ウッドストーブの仕組みや魅力を徹底解説!おすすめアイテムの紹介はもちろん、身近にあるものでウッドストーブを自作する方法もお伝えします!
制作者

川瀬アヤ
キャンプ歴5年。3人の息子や友人とのオートキャンプがメインです。愛車のJEEPで向かう近場キャンプも、フェリーで向かう離島キャンプも最高!カップラーメンとネトフリで過ごす、脱力系スタイルがお気に入りです。相棒はスノーピークの焚火台Mと、ナンガのオーロラライト450DX。長く使うほど味が出る、武骨で丈夫なギアが大好き。ビンテージも気になります。昆虫採集を楽しめるキャンプ場や楽器演奏OKのキャンプ場を日々開拓中!
もっと見る
もくじ
ウッドストーブとは
ウッドストーブとは、ガスやオイルなどの燃料を必要とせず、落ちている木の枝や松ぼっくりなどを使って火をおこすことができる小型のストーブです。焚き火で気になる匂いや、燃え残りが少ないのも特徴。少しの燃料でも強い火力を発揮し、小さな焚き火としても調理用の熱源としても使うことができる便利なアイテムです。
ウッドストーブの仕組み

ウッドストーブの仕組みを知るには、物が燃える原理を知ることが重要です。薪に火を付けると、やがて炎が燃え広がりますよね。見た目では薪自体が燃えているように見えますが、実は、この炎は薪を熱したことにより発生した燃化ガスの燃焼によるもの。これが一次燃焼で、燃え切らない燃化ガスは煙となります。
この燃化ガスを、もう一度燃焼させるのが二次燃焼です。ウッドストーブには二重構造になっているのが特徴ですが、これは残った燃化ガスに空気を送り込み、二次燃焼を促しやすくするため。この仕組みにより、ウッドストーブは燃焼時の煙を減らし、少ない燃料で大きな炎を起こすことが可能になっています。
焚き火台との違い
ウッドストーブはよく焚き火台と混同されます。ウッドストーブと焚き火台は、以下のように燃料や火力、煙の量、用途などに違いがあります。大人数で火を囲み、暖を取りたいなら焚き火台がおすすめ。ウッドストーブは調理や1~2人で美しい炎の揺らめきを楽しむ使い方が向いています。
| 燃料 | 火力 | 煙の量 | 用途 | |
| ウッドストーブ | 枝 落ち葉 ウッドチップ 固形燃料 | 強い 横に広がる | 多い | 調理 1~2人向き |
| 焚き火台 | 薪 炭 固形燃料 | 二次燃焼時は強い 縦に伸びる | 少ない | 焚き火 バーベキュー 大人数向き |
ウッドストーブの選び方
ウッドストーブにはさまざまな種類があり、どう選べばいいかわからない人も多いと思います。ここでは、自分に合ったウッドストーブの選び方を解説します。以下の4つのポイントを理解して、適切にウッドストーブを選びましょう!
【種類】円柱型と箱型の2種類
ウッドストーブはおもに円形型と箱型の2種類が流通しています。それぞれの形状、特徴は以下の通りです。
| 種類 | 円柱型 | 箱型 |
|---|---|---|
| 画像 |  |  |
| 特徴 | 二重構造のものが多く、燃焼効率が高い | 折りたたみできて携行性が高い |
円柱型は熱によって変形しにくい点や、五徳がついていて調理しやすい点もメリットと言えます。一方、箱型は薪をくべる口が大きいことが多く、小枝だけでなく太い薪を使うことで火力を上げられるのも特徴です。
【素材】ステンレスとチタンの違い
流通しているウッドストーブのほとんどがステンレス製、またはチタン製。どちらも丈夫でサビに強いため、さまざまなシーンで活躍します。
チタンは比較的高価ではあるものの、軽量で携行性が高いのがポイント。荷物を軽くしたい登山者やソロキャンパーにもぴったりです。一方、ステンレスは重さがあるものの、リーズナブルに入手できるところがメリットです。ラインナップも豊富なので、素材に迷ったらステンレス製のものをチェックしてみましょう。
【サイズ】大きさは人数に合わせて
ウッドストーブのサイズは、使う人数に合わせて選びましょう。人数に合ったサイズなら、シーンに合わせた調理もしやすくなります。大きさの目安は以下の通りです。
| ソロ | 直径15cm以下 |
|---|---|
| 2〜3人 | 直径15〜30cm程度 |
| 4〜5人 | 直径30cm以上 |
【燃料】固形燃料なども使えると便利
ウッドストーブは、主に枝や木の葉などのを燃料にしますが、場所や季節によっては燃料が調達できないことも。固形燃料や炭も使えるものだと、使用の幅が広がります。固形燃料を置くための皿が付いているかどうかも確認しておきましょう。
【サイズ別】おすすめウッドストーブ18選
ソロ用・2〜3人用・4〜5人用と、サイズ別におすすめのウッドストーブを紹介します。
【ソロ用】直径約15cm以下のウッドストーブ
【2〜3人用】直径15〜30cm程度のウッドストーブ
【4〜5人】直径30cm以上のウッドストーブ
2ステップで簡単!ウッドストーブの使い方
- 小枝や落ち葉、松ぼっくりなどの燃料を入れて着火します。うまく火が付かない場合は紙やペレットなどを着火剤に使いましょう。乾燥した枝や油の多い松の葉などを入れていくと火がおこりやすいです。
- 白い煙が出てきたら、うちわなどで扇いで二次燃焼をサポートします。煙が減り、ダイナミックな炎に変化したら二次燃焼に移った証拠。火力を見ながら燃料を足していきます。カシやケヤキなどの広葉樹は火持ちが良く、燃料追加の手間を減らせますよ。
空き缶でウッドストーブの自作に挑戦!
ウッドストーブは身近なもので自作できるということを知っていましたか?まずはスーパーでよく見かける2種類の缶詰を使ってウッドストーブを作ってみました!
デルモンテのホールトマトといなばのコーン缶がシンデレラフィット!

この2種類の空き缶を使用します。中をよく洗って、紙のラベルをはがしましょう。
大きい缶の下部に穴を開ける

大きい方の缶の下部に、まずは缶切りで穴をあけていきます。酸素を多く取り入れるためにできるだけ多く穴を開けたいので、間隔を狭めにとるのがポイント。

缶切りで開けた穴を、キリやドライバーで広げます。このひと手間で流入する酸素の量が変わってくるので、しっかり穴を広げましょう。
小さい缶の上部と底に穴を開ける

小さい方の缶の上部と底にも同じように缶切りとキリで穴をあけます。
重ねて完成!いざ着火!

すっぽりと重なり、内部にちょうどよい空間ができるので酸素の通り道も確保。まさにシンデレラフィットです!

落ち葉と小枝を入れて着火したところ、無事小さい缶の穴から二次燃焼の炎が上がりました!
調理できるほどの火力にはなりませんでしたが、薪をくべる限りしっかり燃え続けていたので、非常時に暖を取る用途として作り方を覚えておいてもよいかもしれません。
ダイソーグッズでもウッドストーブが自作できた!
カトラリーラックとオイルポットがシンデレラフィット!

ダイソーのこちらの2商品を使って簡単にウッドストーブをつくることができます。まずは紙のラベルをはがします。
オイルポットの下部に穴を開ける

さきほどの空き缶と同じ要領で、オイルポットの下部に穴を開けます。缶切りで簡単に穴を開けることができますよ。
写真左のオイルポットのふたと油濾しは今回使用しませんが、手を加えればスタンドや五徳などのアイテムに変身するかも…?DIYが得意な人はアレンジにもチャレンジしてみてください!
重ねて完成!いざ着火!

カトラリーラックに関してはまったく手を加えることなくオイルポットに重ねるだけで完成!オイルポットの下部に開けた穴がストッパーになり、ほどよい空間ができるので酸素の通り道もしっかり確保できています。

着火すると、カトラリーラックの穴から二次燃焼の炎がしっかり確認できました。空き缶よりも「ウッドストーブらしい」たたずまいを見せ、中の燃料も灰になるまでよく燃えました。
五徳がないので上に調理器具を載せると薪をくべることができず、調理に使うには工夫が必要。アイデアとアレンジ次第で自分にぴったりのアイテムになりそうです。

- 左:手のひらサイズの空き缶ストーブ
- 中:ダイソーアイテムのオイルポットストーブ
- 右:ソロストーブタイタン
ウッドストーブでもっとキャンプを楽しく!
焚き火のワクワク感と、バーナーの手軽さを持ち合わせたウッドストーブ。暖を取るだけでなく調理もできて、燃料も現地調達が可能という非常に魅力的なアイテムです。お気に入りのウッドストーブを購入するもよし、自作で試行錯誤するもよし。ウッドストーブで炎の揺らめきを楽しみましょう。

ポータブルウッドストーブが便利すぎる!お手軽に焚き火を楽しもう!
焚き火をすると、木の燃える香りと炎の温もりを感じられ、アウトドアの雰囲気をさらに引き立ててくれます。そんな焚き火を手軽に楽しみたい、焚き火で沸かしたお湯で美味しいコーヒーを味わいたい人も多いのでは。そこでおすすめなのがポータブルウッドストーブです。今回は便利で携帯の楽なポータブルウッドストーブの種類と使い方をご紹介します。使い方が難しくない?安心してください。超簡単な裏ワザもご紹介します!
今回紹介したアイテム
| 商品画像 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ソロストーブ ソロストーブライト | ソロストーブ ソロストーブタイタン | バーゴ ヘキサゴンウッドストーブ チタン | ユニフレーム ネイチャーストーブ | コニファーコーン パイロマスター2 | キャプテンスタッグ カマド スマートストーブ デルタ | チタンマニア 焚き火台 S | ワンティグリス ROCUBOID ミニ焚き火台 | SOTO ミニ焚き火台 テトラ | YAEI Enthusiast ウッドストーブ ステンレス | DOD ぷちもえファイヤー | tab. 缶ストーブSE | Field to Summit フレイムストーブ20 | Signstek キャンプストーブ 大型 | tab. Field Stove Trigon | huanbush 焚火台 | Field to Summit フレイムストーブMAX | ソロストーブ レンジャーキット2.0 |
| 商品リンク | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見るhinataストアで見る | Amazon で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る |