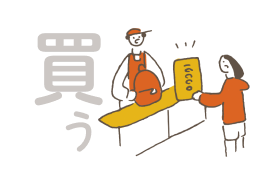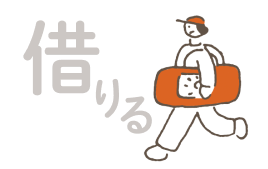出典:PIXTA
キャンプ場でのクマ対策!遭遇しないためには?もし出没したときは?
2025.04.21ノウハウ
日々の喧騒を忘れ、自然と一体になれるキャンプでは野生のクマと遭遇することも。この記事では、そもそもクマと遭遇しないための予防法、もし出会ってしまった時の対策、出没しやすい時期や場所などをご紹介。正しい知識を身につけて安全にキャンプを楽しみましょう!
制作者

川瀬アヤ
キャンプ歴5年。3人の息子や友人とのオートキャンプがメインです。愛車のJEEPで向かう近場キャンプも、フェリーで向かう離島キャンプも最高!カップラーメンとネトフリで過ごす、脱力系スタイルがお気に入りです。相棒はスノーピークの焚火台Mと、ナンガのオーロラライト450DX。長く使うほど味が出る、武骨で丈夫なギアが大好き。ビンテージも気になります。昆虫採集を楽しめるキャンプ場や楽器演奏OKのキャンプ場を日々開拓中!
もっと見る
もくじ
出没しやすい時期は?襲われないためには?クマの生態を理解しよう

出典:PIXTA
自然の中でのんびりと過ごすキャンプ。しかし、そこは動物たちの生息地。特に気をつけるべきは、クマとの遭遇や被害です。過去にはキャンパーがクマに襲われたというケースも。そんなクマとアウトドア中に遭遇しないための予防法、もし出会ってしまった時の対策などを紹介します。
北海道はヒグマ、本州はツキノワグマ
日本では北海道にのみ生息する「ヒグマ」と、本州と四国に生息する「ツキノワグマ」がいます。かつては九州にもツキノワグマがいましたが、現在その生息は確認されていません。クマは北海道の55%、本州四国の45%の地域に生息しているとされ、思いのほか「他人事ではない」存在だということがわかります。
ヒグマは肉食類に分類されていますが肉食を含む雑食性で、鳥や昆虫、鹿の死骸、木の実などを食べます。一方でツキノワグマは草食性です。
クマが出没しやすい時期
クマは地域にもよりますが11月ごろから冬眠をはじめ、3月〜5月ごろに冬眠を終えます。つまりクマは春〜秋にかけ活動・出没するということ。
春〜秋はいつでもクマが出没しておかしくないのですが、クマは冬眠の間飲まず食わずであることや、メスは冬眠中に出産することなどから冬眠前の秋には特に栄養を蓄える必要があるという点も意識しておくとよいでしょう。
クマは人を襲う?クマが凶暴になる理由
そもそもクマは臆病で、クマがその優れた嗅覚で人間の存在に気付いたときは、クマの方から人間を避けて遠ざかってくれているそう。ではどのようなときにクマは人間に対して凶暴化するのでしょうか。理由を挙げてみます。
- 人間が自分に向かってきたと思って驚いた
- 母グマが子グマを危険から守ろうとした
- 自分の餌を横取りされそうになった
おもにこのような理由が挙げられますが、いずれもクマに「敵だと認識させてしまった」「動揺させてしまった」ことが原因と言えるでしょう。
クマに遭遇しないために!キャンプ場の選び方

出典:PIXTA
お伝えしたように、クマは臆病で基本的には用も無くキャンプ場に近づくようなことはありません。しかしキャンプ場にクマが出没、人を襲う事故も発生しており、キャンプ場でクマと出会う可能性はゼロとは言えないのです。
まずはクマに遭遇しないために、どのようにしてキャンプ場を選べばよいのでしょうか。
キャンプ場の情報をチェック

出典:PIXTA
まず、お目当てのキャンプ場やその周辺でクマが出没したことがあるかどうか、過去にさかのぼって調べてみましょう。もしクマが出没する可能性のある地域でも、キャンプ利用者や観光客向けの講習会が開催されていたり、キャンプサイトの見通しを確保するよう整備したりと、しっかりクマ対策が取られている場合もあります。
また、危険だと判断された場合にはキャンプ場が一時閉鎖される場合があることも頭に入れておきましょう。
自治体からの情報提供
自治体でもクマの出没情報をウェブサイトなどで公開しています。直近や過去のクマの動向をチェックするほか、自治体からの注意喚起などが無いかどうか、最新の情報を入手しておきましょう。
参考:東京都「都内での目撃情報」
参考:北海道「市町村ヒグマ関連情報リンク集」
クマの出没に限らず、キャンプ場を決めるときはいざというとき適切に対応できる場所を選ぶことが鉄則。過度に怖がる必要はありませんが、現地の正しい情報を得ること、現場の指示に従うこと、不安な場合は無理にキャンプに行かないことを心がけましょう。キャンプ中に徹底すべきクマ対策

出典:PIXTA
キャンプ中にクマを呼び寄せないようにするために人間ができること、すべきことはなんでしょうか。クマとの遭遇を避けるために実践したい対策を紹介します。
残飯を放置しない

出典:PIXTA
これはクマに限らずほかの野生動物を寄せ付けないためにも大切なことですが、飲食後の残飯をにおいが漏れるような状態で放置しないようにしましょう。クマの嗅覚は、一般的に「鼻が効く」とされる犬よりさらに7〜8倍も優れており、なんと1km先のにおいも嗅ぎつけることができるとか。
「これぐらいなら大丈夫かな」と油断せず、残飯はキャンプ場の指示にしたがって適切に処理しましょう。夜間はゴミをふたつきのゴミ箱に入れ、車内に隠しておくことも大切です。
人間の存在を知らせる
クマはもともと臆病なので、人間の存在を察知すればクマの方から人間を避けてくれます。そのためラジオなどで小さく音を出しておき、人間の存在をクマに知らせることも有効。クマは嗅覚のほかに聴覚もとても優れているので、周囲の迷惑にならない程度の小さな音量でも効果があります。
鈴や焚き火はクマ避けに効果ある?
鈴
クマ対策グッズとして最初に挙がることも多いのが「鈴」です。鈴を身につけて鳴らすことで「人間の存在を知らせる」効果があるのでクマ避けには有効だとされています。
焚き火

出典:PIXTA
キャンパーの中には「動物は火を怖がるので、クマ避けに焚き火は有効ではないか」と考える人もいるかもしれません。しかしクマは火を怖がる習性がないため、焚き火は直接的にクマ避けになるとはいえません。
ただし、一度人間に痛い目に遭わされた経験のあるクマは、焚き火によって人間の存在を察知して逃げていくとも言われています。
クマをおびきよせないために
ここまでにお伝えしたような方法で、クマの方から人間を避けてくれるよう働きかけるのがクマ対策として一般的です。しかし人間の食べ物を食べてひとたびその味を占めてしまったクマは、また人のいるところへ近づきかねません。鈴の音を聞いて逆に近寄ってくる可能性もあるのです。
まずはクマを人間や人間の食べ物に近寄らせないことが何より大切だということを、私たちは肝に銘じなくてはいけません。
もしもクマが出没したら
不意にクマに遭遇してしまったらどのように対処すればよいのでしょうか。3つのシチュエーションごとに対応方法を紹介します。
遠くにクマを見つけた場合
遠くの方でクマを見つけた場合は、クマが人間に気付いていればクマの方から立ち去る場合が多いため、静かにその場を立ち去りましょう。急な動きをしたり恐怖のあまり叫んだりしてしまうと、クマが驚いて何をするかわかりません。落ち着いて行動することが何より大切です。
近くでクマを見つけた場合
近くでクマを見つけた場合、ときにクマが向かってくることがありますが、慌てて走って逃げてはいけません。本気の攻撃ではなく「威嚇突進」という、止まって引き返すような行動を見せる場合がありますが、その際は落ち着いてクマとの距離を取ることでクマが立ち去る場合があります。
クマは逃げるものを追う習性があるので、決して背中を見せないようクマの方を向いたままゆっくり後退しましょう。
至近距離でクマに遭遇した場合
クマが直接攻撃などの過激な反応をしめす可能性が高くなります。攻撃を完全に回避する方法はないため、頭部や顔などを手で覆い、直ちにうつ伏せになってダメージを最小限にとどめる行動をとりましょう。
クマ撃退スプレーを持っている場合、クマに向けて噴射することで攻撃を回避できる可能性が高くなります。
環境省より「クマ類の出没対応マニュアル」が配布されています。クマ対策についての解説や資料は一度目を通しておくとより安心です。
過度に怖がらず、自然と共存を
クマはもともと臆病で、キャンプ場に近づくことや人間に危害を加える可能性は高くありません。クマが人間にとっての問題行動を起こす原因は人間にあることが多いということを、しっかり心に留めて行動したいですね。
キャンパーとして自然や野生の動物といいお付き合いができるよう、正しい知識と情報を持って安全なキャンプを楽しみましょう!
今回紹介したアイテム
| 商品画像 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | クイックキャンプ ミニトラッシュボックス | オレゴニアンキャンパー ポップアップ トラッシュボックス R2 | OHM(オーム) AM/FMアウトドアラジオ | 冒険倶楽部 AY-12 | キャプテンスタッグ ベアー クマすず&ホイッスル付 | ポリスマグナム 熊撃退スプレー |
| 商品リンク | Amazon で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | 楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る楽天市場 で見るYahoo! で見る | Amazon で見る |